『こころのマネジメント』
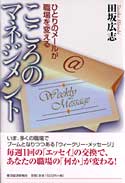

- 出版社
- 東洋経済新報社
- 出版日
- 1999年2月
職場の文化を、どうすれば変えていけるのか?
そうした問いを胸に抱いて、
日々の仕事に取り組んでいるマネジャーやビジネスマンは
少なくないでしょう。
もとより、この問いに安易な答えなどないのですが、
一つ理解しておくべきことがあります。
それは、「職場の文化」とは、
その職場に集まったメンバーのこころが集まって生み出す
「こころの生態系」を映し出しているということです。
では、その「こころの生態系」に、
どうやって働きかけていけばよいのでしょうか?
この本では、そのための一つの方法として、
「ウィークリー・メッセージ」という手法を提案しています。
この方法を実践するだけで、
「職場の文化」は自然に変わっていくでしょう。
しかし、このウィークリー・メッセージは、
同時に、その職場のマネジャーのマネジメントを映し出す「鏡」でもあるのです。
新しい時代のマネジメントへの進化は、
まず、その「鏡」を覗き込むことから始まるのです。
- 目次
プロローグ 月曜日の朝に吹く風
第1章 仲間を理解する新しいスタイル
第2章 自然に対話が生まれるとき
第3章 しなやかに格闘する個性
第4章 知識を学びあうために
第5章 智恵はひそやかに伝わる
第6章 書くことによるこころの成長
第7章 こころの生態系をみつめて
第8章 マネジメントを映し出す鏡
エピローグ ロビンソン・クルーソーの一冊
評者からのメッセージ
読者からのメッセージ (本書のご感想を、ぜひともお寄せください。)
50代 公務員
『こころのマネジメント』でウィークリーメッセージを知って以来、
職場で毎週身近な出来事を発信し続けています。
会社員
1年程前から 複雑系について興味もち、
その体系を勉強しておりましたとき、ご著書に巡り合いました。
『複雑系の知』から始まり、
『暗黙知の経営』を含め『こころのマネジメント』まで計8冊ほど拝読しておりますが、
その都度新しい発見があり、 感謝しております。
日頃意識せずに行ってきた私たちの行動が、
どこから来ているものかを考える機会を与えて頂いています。
ご著書はどれも言葉では語れぬほど私のこころ(思想)に沁みいってくる内容であり、
また講演は冒頭に話されたようにイメ-ジを一変させるほどの強烈なもので、
より一層のファンになってしまいました。
理数系から哲学系まで、本当に幅広い知識の裏付けをもたれたお話を
今後もうかがえる機会がありましたら、ご教示頂ければ幸甚です。
会社員
田坂さん、感動を与えていただき、ありがとうございました。
タンポポの話には感動しました。
田坂さんの本は、何冊か読ませていただきました。
中間管理職を叱咤するもの、
ウィークリー・メッセージのすばらしさを書かれたもの、
金融の未来の姿に関するもの。
いずれも読むうちに引き込まれ、
時間を忘れてしまうことがしばしばでした。
私は、今42歳です。
中間管理職として、これからの生き方を模索しているところです。
そんな時、田坂さんの本を読み、
まだまだこれからだと元気づけられました。
これからも、田坂さんの書かれた本を
自分の体験に生かしていきたいと思っています。
是非、書き続けてください。

