『なぜ日本企業では情報共有が進まないのか』
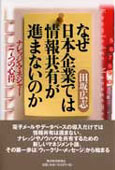
- 出版社
- 生産性出版
- 出版日
- 1999年2月
Kindle版あり
「情報化」とは、
パソコンを導入し、使いこなすことであるという誤解があります。
言葉を換えれば、情報化とは、
「情報機器の扱い」が上手になることだと考えているのです。
しかし、そうではありません。
情報化とは、「情報の扱い」が上手になることなのです。
では、「情報の扱い」が上手になるためには、どうすれば良いのか?
この本では、その心得について語っています。
- 目次
はじめに マネジャーからナレッジ・マネジャーへ
第一の心得 情報機器の扱いではなく情報の扱いに熟達する
第二の心得 データ、ナレッジ、ノウハウを区別して扱う
第三の心得 膨大なデータのなかから直観的に要点をつかみ取る
第四の心得 生きた言葉でメンバーにナレッジを伝える
第五の心得 協働作業を通じてノウハウの共有を進める
第六の心得 情報ボランティアの企業文化を育てる
第七の心得 職場に相互理解による共感の場を生み出す
おわりに 「こころの生態系」のマネジメントへ
評者からのメッセージ
読者からのメッセージ (本書のご感想を、ぜひともお寄せください。)
40代 会社員
『なぜ日本企業では情報共有が進まないのか』を拝読しました。
この4月から30人弱のメンバーを率いる組織を任せられました。
本書の中にあった
「ウィークリーメッセージ」を実践してみようと考えています。
二つの会社が統合してできた新しい組織ですので、
吸収された側の企業のメンバーが白けないで乗って来てくれるかどうか、
いささか気がかりなのが現状です。
会社員
たった今、『なぜ日本企業では情報共有が進まないのか』を読み終えて、
このメールを書いています。
『創発型ミドルの時代』
『なぜ日本企業では情報共有が進まないのか』
を読ませていただいた感想を書いてみたいと思います。
心得その1から始まって7項目の中で、
たった1ヶ所、意外だと思った記述があります。
それは、
「プロフェッショナルとして評価の高い人間にかぎって、
不思議なほど人格者であるという意外性」と書かれていたことです。
私は常々、
「専門的知識、技術を駆使して
Q、C、Dを守りながらやり遂げる能力がある人」
「人心を収攬できる人間的な魅力がある人」をプロフェッショナルだと思っていました。
技術力や専門性に特化しただけの人格の無い人間は、
単なるスペシャリストではないかと思います。
極論ですが、スペシャリストに人格が備わるとプロフェッショナルに近づく、
と言ったほうが良いかもしれません。
とは言いつつも、2冊の本はうなづくことばかりで、
仕事をする上でも勇気づけられます。
7つの心得となっていますが、
やっぱり最後の「こころの生態系」にすべてが帰結されると思います。
私は小さいながらも一つの課を任されて、
パソコンを中心にしたソフトウエア開発を業務として行っています。
いつも課のメンバーに、
「どう人の役に立つかを考え、実行することにこそ人間の存在意義があり、
そのためにお金をもらうのがビジネス、
もらわないのがボランティアだ」
と言ってきました。
「両方のバランスを考え生きて行く必要があり、
どちらが突出してもダメだ」
とも言ってきました。
そういう考えに共鳴してくれたら、
あとは自然に七つの心得は達成されていくものだと楽観的に構えています。
ただし、決して考え方を押し売りしている訳ではありません。
手前味噌ですが、結構共感を得ているようです。
やっぱり人間に関する知識がすべてであり、
時代を超えて普遍的であると思います。
長々と書いてしまいましたが、
先生の本は自分の考えが間違っていないという安心感を与えてくれます。
次作も期待しております。
50代 会社員
数年前に、田坂さんがどのような方かを知らずに購入した本をお読みして、
最初の印象は「きれい事を書いている」でした。
しかし、その後の小生の実体験は仮説検証法と同様の世界であり、
田坂さんのおっしゃることがズバズバと分かりました。
まさに、田坂さんが書いていらっしゃることは、「うーん、なるほどー」であり、
小生の頭の中でこれまでもやもやしていたものがくっきりとした次第です。
田坂さんの著書の2冊目を購入した際も、
あとから著者が田坂さんだと認識した次第です。
その後は田坂さんの本を探して購入するようになりました。
田坂さんの著書を拝読して、大げさかも知れませんが、
「考えること」が楽しくなり、人生が変わりました。
ちなみに小生は、社会人になる前は「機械工学」を勉強し、
社会人としては長年「機械設計」の世界におりました。
その後「海外駐在」を経験し、最近では「お客様相談室」の仕事をしております。
人と接する中で、田坂さんの著書から得た事が、
小生の頭の中で大いに役立っております。
これからも田坂さんの影響を大いに受け続けることになると思っております。
よろしくお願いします。

